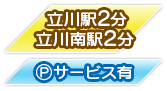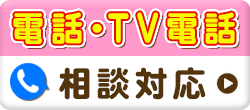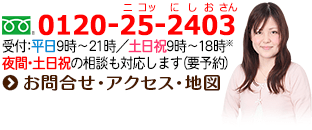学習障害で障害年金が受け取れる場合
1 学習障害も障害年金受給の対象となる場合があります
学習障害は、発達障害の症状の1つに分類されており、発達障害は障害年金受給の対象とされています。
そのため、障害年金受給にあたっての各要件を満たしていれば、学習障害の方も障害年金を受け取れることになります。
2 初診日
障害年金の申請にあたっては、初診日(申請傷病に関して初めて医療機関を受診した日)が重要となります。
学習障害の場合、障害があるものとして幼少期に通院をはじめる方もいれば、「単に成績が悪い、勉強が得意ではないだけ」という周囲の判断により、大人になるまで通院自体されない方もいると思います。
幼少期に通院されている場合、過去の通院の事実を診断書、カルテ等で明らかにできるかが1つの問題点となることがあります。
3 保険料納付
初診日が20歳を超えている場合、保険料納付も問題となってきます。
年金保険料が一定以上未納となっていると、そもそも障害年金を受け取ること自体ができません。
保険料納付については、①初診日の属する月の前々月まで直近1年間未納がないか、②初診日の前々月までの全年金加入期間の1/3以上未納がないかのどちらかを満たしている必要があります。
保険料納付の免除手続きを行った場合、免除された月は未納とされませんが、判断は初診日の前日時点を基準時として行われますので、未納の月について初診日以降に免除手続きをしても、遡って要件を満たすことにはなりませんので注意が必要です。
なお、初診日が20歳前の場合には、まだ保険料納付の義務が発生していないため、保険料納付の要件は問題となりません。
4 障害状態
学習障害の場合、上記2つの要件を満たしており、かつ、一定の障害状態であるという要件を満たしていると認められることにより、最終的に受給が認められることになります。
例えば、学習障害を含む発達障害の障害年金2級の認定基準は、「発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの」という基準になっています。
もっとも、学習障害について、どの程度の症状であれば「コミュニケーション能力が乏しい」といえる、どのような行動が「不適応な行動」なのか、はっきりと数値化された基準があるわけではありません。
一定水準以上の労働への影響があれば3級程度、日常生活に著しい制限があると認められる場合には2級程度とされていますが、軽度の学習障害のみ発現している方の場合、仕事自体はできており、収入も得られているような方も少なからずいます。
そういった方の場合、学習障害のみでは障害状態の判断により、障害年金を受け取れない場合もあります。
一方、学習障害と合わせて、うつ病や知的障害等も認められている場合、それらの傷病と合わせて障害状態が認められ、障害年金を受け取れる場合もあります。